「自社メディアの記事制作を外注したいけれど、どんな制作代行を選べば良いか分からない」
「コストや品質面で失敗は避けたい」
そんな悩みを抱えていませんか?
昨今、コンテンツマーケティングの重要性が高まり、専門性のある記事を効率的に制作するために外注を検討する企業は増えています。
しかし、外注先によっては料金体系や得意分野、対応範囲などが大きく異なるため、自社の目的に合ったパートナー選びが欠かせません。
本記事では、Webマーケティング・SEOの分野に特化した筆者が、記事制作代行の選び方や外注先を選ぶ際のポイント・注意点を解説します。
自社メディアの記事を外注したいとお考えの方はぜひ、参考にしてください。
目次
記事制作の外注を考える企業が増えている背景には、主に「リソース不足」「専門的なクオリティを求める必要性」「業界の最新トレンドへの対応難しさ」などがあります。
最近のGoogleアルゴリズムはE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)の要素を重視しており、高品質なコンテンツの継続提供が求められる時代になりました。
これを自社だけで行うのは難しい場合があり、外注は効率的かつ効果的な選択肢となります。
一方、依頼先選定を誤ると、コストだけがかかって成果につながりづらいケースも考えられるため、慎重に検討することが大切です。
外注を検討する多くの企業は、以下のような課題を社内で抱えています。適切な体制を整えないまま担当者に制作を任せると、コンテンツ戦略そのものが形骸化するリスクもあるため注意が必要です。
マーケティング担当者はSEO対策だけでなく、SNS運用や広告運用なども同時並行で行っていることが多く、記事制作に割ける時間が限られます。結果的に公開までのスピードが遅れ、競合他社に後れを取ってしまうケースが出てきます。
記事の質を高めるにはブランドイメージに合った文体や表現方法を徹底し、誤字脱字がないか、情報源は信頼できるかなど多角的にチェックしなければなりません。社内だけでは専門的な見識や十分な校閲体制が整わない場合もあるため、外注を検討する企業が多いのです。
Googleは定期的に検索アルゴリズムをアップデートし、E-E-A-Tやユーザーエクスペリエンスを重視した評価が進んでいます。これらの動向を継続的に学習し、記事に反映させるには知識のアップデートが必須ですが、社内リソースだけでは対応しきれないこともあります。
外注には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。依頼する際には、双方を正しく理解したうえで判断することが重要です。
まずリソースの効率的な活用が挙げられます。制作の専門家に依頼すれば、クオリティの高い記事をスピーディに仕上げられ、自社スタッフは戦略立案や施策の実行に注力できます。また、業界動向やSEOノウハウを豊富に持つパートナーと協力することで、E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作が容易になる点も大きな魅力です。
一方で、外注コストの発生や社内との認識違いが生じるリスクがあります。ブランドの方向性や制作ガイドラインを外注先に共有しきれないと、納品された記事が意図したイメージと異なる可能性も。これを防ぐには、契約前のすり合わせやブラッシュアップの工程を十分に設ける必要があります。
外注先選びで失敗しないためには、以下の5つのポイントが重要です。目的や実績、コミュニケーションなどをしっかり確認したうえで依頼することで、スムーズな進行と高い成果が期待できます。
「何のために記事を作るのか?」を明確にすることで、外注先との方向性のズレを防げます。集客重視なのか、エキスパート感のある専門記事で信頼度を高めたいのか、あるいは商品認知を広げたいのかによって、記事のテイストや構成は変わってきます。
ビジネスゴールを言語化することで、外注先に正確な意図を伝えられます。例えば「○件の問い合わせ数増加」「月間○PV達成」のように数値目標を設定すれば、依頼内容がより具体的になり、適切な戦略を共同で立案しやすくなります。
PV数や滞在時間、CVRなどをKPIとして設定することで、記事公開後も成果を客観的に測定できます。KPIが明確であれば、記事制作の優先順位や改善の指標も定めやすく、外注先との協議に生産性をもたらします。
外注先がどのようなジャンルを得意としているか、過去の事例から確認しましょう。金融や医療、ITなど、高度な専門知識が必要な分野は特に、実績を重視することでリスクを低減できます。
可能であれば実際に公開されている記事を読んでみるのが最も確実です。文章構成や内容の網羅性、SEO施策の有無をチェックしましょう。公開実績がない場合はサンプル作成を依頼し、書き手のスキルやコミュニケーション力を見極めることも大切です。
一部のライターは得意領域を絞って活動しており、深い知識を持っている場合があります。自社の事業領域やターゲット層にマッチするライターや制作会社を探すことで、より効果的なコンテンツを得られる可能性が高まります。
外注先と頻繁に連絡を取り合い、進捗管理をしやすい環境を作ることが成功の鍵です。特に修正が発生する際はコミュニケーションの精度が成果物に直結します。
チャットツールやメール、オンライン会議などでどの程度の頻度で打ち合わせを行うのか、あらかじめ明確にしておきましょう。例えば「週1回の定例ミーティング」「納品前に最終チェックの場を設ける」など、スケジュールを決めておくと管理がスムーズです。
記事を完成形に近づけるためには、修正依頼とフィードバックが欠かせません。たとえばGoogleドキュメントなど、リアルタイムで共同作業ができるツールを活用すれば、意思疎通の齟齬を減らせるでしょう。修正ポリシーも事前に確認し、どこまで対応してもらえるのかを把握しておくことも大切です。
料金は外注検討時の大きなポイントです。目安として、1記事あたり数千円から数万円まで幅広く、専門性や取材の有無によって変動します。複数の外注先を比較し、単に安さだけでなく成果が出るかどうかを見極めましょう。
文字単価は「文章量に応じて料金が増減」し、記事単価は「内容のボリュームにかかわらず同一料金」です。それぞれ一長一短があり、長文でも固定料金の方が得になるケースや、短めの記事量で質の高いコンテンツを複数作りたい場合に文字単価制が適しているケースなどがあります。
見積もりを依頼する際は下記の項目も忘れずに確認しましょう。特に修正対応範囲や納品形式は、トラブル回避のために具体的な数字や形式で明文化しておくと安心です。
これらを事前に把握することで、後から追加費用が発生するリスクを減らせます。契約内容に含まれない作業がどの段階で発生するかを想定しておくのもポイントです。
細かな対応範囲を確認し、双方の認識を一致させておくと、納品後の「想定と違った」という問題を防ぎやすくなります。取材・写真撮影や著作権の取り扱い、納品形式などをあらかじめ整理しておくことが大切です。
現地取材や写真撮影を行う記事制作は費用が高くなる場合があります。取材対象や撮影の可否、どのような写真を求めるかを具体的に整理し、見積もりの段階で依頼先に伝えておきましょう。必要に応じてクライアント側でカメラマンを手配するケースもあります。
WordやGoogleドキュメント、CMSへの直接入稿など、どの形で納品するかによって作業量は変わります。また、完成した記事の著作権を誰が持つのかを明確にすることで、後々の再利用や加筆修正がスムーズになります。特にコーポレートサイトでの利用や他媒体への転載などを想定している場合は要注意です。
記事制作の外注先としては、「専門ライター」「クラウドソーシング」「制作会社・広告代理店」などが挙げられます。それぞれに強み・弱みがあるため、自社が何を重視するかに合わせて選択するのが得策です。
得意分野をもつライターと直接やり取りを行うことで、連絡の融通が利きやすく、きめ細かい要望に応えやすいのが強みです。ただし複数ジャンルの記事をまとめて依頼したい場合は、担当ライターが足りず外注先を増やす必要が出るなど、管理の手間が増すリスクがあります。
登録している多数のライターに対して、一度に複数の案件を公開できる柔軟性が魅力です。単発の仕事を大量にさばきたい場合に適していますが、ライターのスキルや安定性がまちまちなため、一定の品質を確保するには発注側のチェック体制やディレクション力が不可欠です。
大規模なコンテンツプロジェクトや、マーケティング戦略の構築から担当してほしい場合に有力な選択肢です。社内ディレクターが品質や納期を管理してくれることが多く、安定したクオリティを期待できます。ただし費用が高めになる傾向があるため、コスト対効果を十分に検討しましょう。
一般的な料金相場として、文字単価であれば1円~10円程度、記事単価であれば5,000円~20,000円程度が目安とされています。ただし、専門知識が必要なジャンルや取材が必要な場合は単価が上がりやすくなります。費用対効果を正しく判断するには、公開後のPVやお問い合わせ数など定量的な指標に加え、ブランドイメージ向上や検索エンジンからの評価(E-E-A-Tを含む)も考慮に入れることが大切です。安いだけで決めると、成果が出ずに追加コストが膨らむ可能性もあるため注意しましょう。
外注にはメリットがある反面、想定外のトラブルが発生する可能性もゼロではありません。下記の注意点を把握しておくことで、失敗リスクを大きく減らせます。
納期に間に合わない、連絡が途絶えるなどの事態を回避するには、契約前に目安となるスケジュールを共有し、進捗確認の場を定期的に設けることが大切です。契約書には「○月○日までに第1稿提出」といった形で、具体的な期限を示すとより確実になります。
全てを外注先任せにするのではなく、社内で校閲担当を設置するなど二重チェック体制を整えると安心です。特に専門性の高い分野では、事実関係の確認や最新情報の反映が欠かせません。時間が許すならば、完成原稿を複数人でレビューすることで漏れを減らせます。
執筆した記事が第三者の権利を侵害していないかどうかや、著作権をどちらが保有するのかはしっかり契約書に明記しておきましょう。特に他サイトからの画像引用や翻訳記事などを扱う場合は、外注先と綿密にコミュニケーションを取り、法的トラブルを未然に防ぐ必要があります。
記事を公開して終わりではなく、アクセス解析ツールを用いてPVや離脱率、コンバージョンに関するデータを把握し、必要に応じてリライトを行いましょう。検索アルゴリズムの変更や新たな競合記事の出現にも対応するため、定期的な見直しが欠かせません。
記事制作を外注する際は、目的の明確化や実績確認、円滑なコミュニケーション手段の確立などを意識することでトラブルを減らし、成果に直結させやすくなります。
さらに、E-E-A-Tを意識した高品質なコンテンツ制作を目指すためには、外注先と協力して継続的なアップデートや検証を行うことが重要です。
コストだけで判断するのではなく、自社のブランドや目標に合うパートナーを見つけることで、外注の効果を最大限に高められるでしょう。
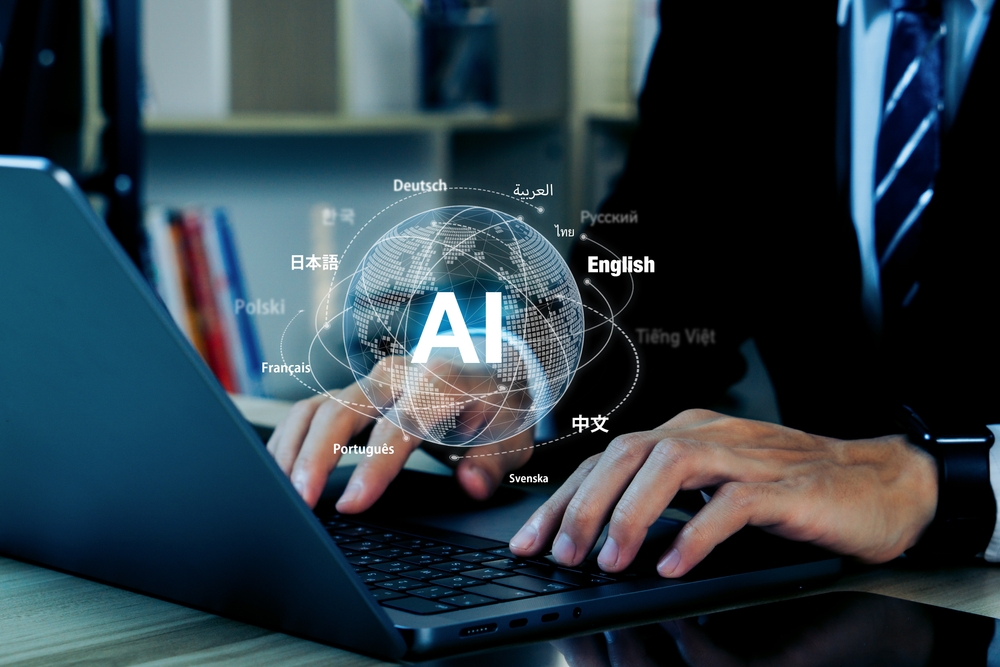
SEO対策をしたいけど「方法がわからない」「リソースが足りない」という際はProteaにご相談ください。
サイトの状況を確認し、各社の課題にあった提案をさせていただきます。
お問合せはこちら
また、AI記事サービスの「AIフォースSEO」も提供しております。
AIフォースSEOは1記事5,000円から作成可能な記事生成サービスです。
キーワード選定がプラスされたプランもご用意しております。
SEO対策を実施したいけど、自社にノウハウがない、リソースが足りないなどでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
AIフォースSEOのお問合せはこちら
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。