「メタディスクリプションの文字数って何文字が最適?」「そもそもSEOに効果あるの?」——こんな疑問を抱えたことはありませんか?
検索結果に表示されるメタディスクリプションは、ユーザーのクリック率を左右する重要な要素です。しかし、最適な文字数や書き方を誤ると、情報が省略されたり、逆に表示されないこともあります。
この記事では、最新の検索結果表示傾向をもとに「最適な文字数」や「効果的な書き方」を徹底解説します。さらに、SEO観点から見たメタディスクリプションの役割や、クリック率を高めるポイントも紹介します。
自社のWeb担当者になり、メタディスクリプションの事を知りたい!とお考えの方は是非、参考にしてください。
目次

まずは、メタディスクリプションの基本的な意味と、検索結果上での表示形式、そしてユーザーのクリック行動に与える影響について整理しましょう。SEO施策の一環としての重要性を理解することが第一歩です。
メタディスクリプションとは、HTMLのhead内に記述されるmetaタグの一種で、ページの内容を要約して説明するテキストです。検索結果のスニペット(説明文)としてGoogleなどの検索エンジンに表示され、ユーザーがそのページを訪問するかどうかの判断材料となります。SEOにおいては直接的な順位要因ではないものの、クリック率(CTR)に強く関与するため、間接的なSEO効果が期待できます。
Googleの検索結果では、タイトル(titleタグ)の下にメタディスクリプションが表示されます。ただし、必ずしもmetaタグの内容がそのまま表示されるわけではなく、検索キーワードとの関連性が高い文言が自動で抽出・表示されるケースもあります。それでも、明確で魅力的なメタディスクリプションを書くことは、CTRを高める施策として有効です。
メタディスクリプションは、ユーザーが検索結果をスクロールして情報を比較する中で、「このページに自分の欲しい情報があるかどうか」を判断する重要な要素です。例えば、同じキーワードで複数のページが表示された場合、「料金相場がわかる」「図解で解説」などの具体性を持ったディスクリプションの方がクリックされやすくなります。明確なベネフィットや特徴を盛り込むことで、他の検索結果との差別化が図れ、CTR向上につながります。

メタディスクリプションは単なる説明文ではなく、表示される文字数によってその効果が大きく左右されます。文字数の最適化がなぜ必要なのかを明確にすることで、効果的な記述の重要性が理解できます。
Google検索では、メタディスクリプションの表示可能な文字数には上限があります。一般的にPCでは約120〜160文字、スマホでは約50〜90文字程度とされており、それを超えると「…」で省略されてしまいます。これはユーザー体験向上のため、視認性と簡潔性を重視しているためです。
ユーザーは検索結果の中で複数の情報を比較検討しており、ディスクリプションが読みやすく、かつ知りたい内容にマッチしているとクリック率が高まります。逆に、長すぎたり情報が断片的でわかりづらい場合、他の検索結果に流れてしまう可能性があります。そのため、「表示される範囲内」で内容を端的に伝えることが求められます。
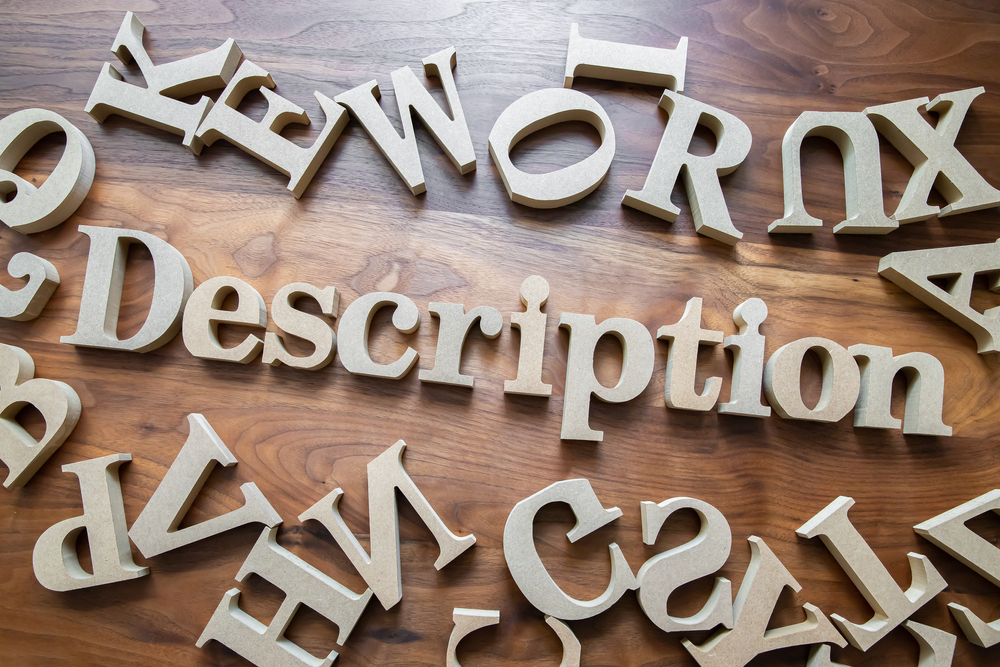
ここでは、PC・スマホそれぞれでの表示文字数の違いや、実際のGoogle検索結果を参考にした文字数傾向、またブランド名やタイトルとのバランスの取り方など、実務で役立つ情報を整理して紹介します。
Google検索結果におけるメタディスクリプションの表示文字数は、デバイスによって異なります。PCでは最大160文字前後まで表示されることが多いのに対し、スマートフォンではおよそ90文字前後に収まる傾向にあります。したがって、重要な情報は前半に配置することが鉄則です。長文を記述した場合でも、省略された際に要点が伝わる構成にしておく必要があります。
表示がカットされない文字数の目安は、PCで120〜140文字、スマホで60〜80文字程度と考えるとよいでしょう。ここで重要なのは、検索エンジンは「文字数」ではなく「ピクセル幅」で表示を判断しているという点です。
例えば、全角文字や英語、数字の使用頻度によっても実際の表示範囲は変化します。これに対応するには、シミュレーションツールを併用して確認することが現実的かつ効果的です。
実際のGoogle検索結果では、metaタグの内容がそのまま表示されるとは限りません。例えば、metaディスクリプションに書かれていない内容がページ本文にあり、それが検索クエリと強く関連している場合、Googleがそちらの文を優先的に表示する傾向があります。特に、metaが曖昧であったり、タイトルや本文と整合性がない場合は、自動的に書き換えられる確率が高くなります。

SEOの観点から見ても、クリック率(CTR)に影響を与えるメタディスクリプションは、検索意図の理解と自然なキーワード配置が鍵を握ります。ここでは、実践的な書き方のコツやユーザー行動を促すテクニックを紹介します。
検索ユーザーは、自分の知りたい情報に最も素早くアクセスできるページを選びます。そのため、検索キーワードの背景にある「なぜその言葉で検索したのか(検索意図)」を考慮したディスクリプションが重要です。
検索意図は大きく分けて以下の3つに分類できます。
例えば、「SEOツール 比較」で検索された場合、「主要ツール5選を特徴・料金別に徹底比較」といったディスクリプションであれば、ユーザーの比較意図にマッチします。検索意図に合わせた具体的な訴求がCTR向上に直結します。
Googleはキーワードの出現有無よりも「文脈に沿った自然な使用」を重視しています。無理に繰り返すのではなく、1回〜2回程度を目安に、ユーザーが検索しそうな語句を自然な文章の中に組み込みましょう。
例えば「メタディスクリプション 文字数」がキーワードなら、「メタディスクリプションの最適な文字数と省略されない書き方を解説します」といった表現で、読者に伝わりやすく検索意図とも一致します。詰め込みではなく、違和感なく馴染む言い回しを意識しましょう。
メタディスクリプションには、ユーザーが思わずクリックしたくなるような「行動喚起(CTA)」を含めるのが有効です。これは広告文のライティング技術と似ており、短い文章内で価値提案や安心感を伝えることがポイントです。
CTAは単に「見てください」という誘導ではなく、ユーザーの心理に訴えるフレーズである必要があります。例えば、
このように、メリットを明示しながら期待を煽る構成が効果的です。ただし、内容と一致しない誇大表現や釣りタイトル的な記述は信頼性を損なうため避けるべきです。
ユーザーが「この先に答えがある」と感じられるような構成を意識することが重要です。具体的には以下のようなフレーズが効果的です。
これらのフレーズは、検索結果の中で他ページとの差別化を図り、ユーザーの「知りたい欲求」に訴求するものです。ただし、本文でそれらを裏切らない内容であることが大前提です。
メタディスクリプションは、1〜2文で内容を完結させる必要があります。構文はシンプルに保ち、読点(、)や句点(。)を適切に配置してリズムよく読めるようにしましょう。改行は検索結果では無視されるため、一文内で完結できるよう、要点をコンパクトにまとめることが大切です。
例えば、「このツールを使えば、初心者でも簡単にSEO対策ができるようになります」といった構成は、自然かつ行動につながる文の良い例です。冗長な修飾語や二重表現は削り、内容の密度を意識しましょう。

効果的なメタディスクリプションを作成するには、「避けるべき表現」や「逆効果となる記述」を理解しておく必要があります。CTRを下げてしまう失敗例をあらかじめ把握し、未然に防ぎましょう。
「SEO」「SEO対策」「SEO施策」などとキーワードを羅列するような記述は、読みづらさを助長し、Googleからもユーザビリティが低いと判断される可能性があります。検索ユーザーも、過剰なキーワードの詰め込みは「不自然」と感じやすいため、結果的にクリックを避けられる原因にもなります。1つの文にキーワードは1回までが目安です。
「役に立つ情報が満載!」「ぜひご覧ください」など、内容が具体的でない表現は、ユーザーの行動を促すには不十分です。クリックした後の価値がイメージできないため、他のページに流れてしまう原因になります。
例えば以下のような悪例があります。
これでは、どんな情報があるのか、どんな問題を解決できるのかが見えてきません。「◯◯の使い方を図解で紹介」「初心者がつまずきやすい点を丁寧に解説」など、明確な価値提案を盛り込むようにしましょう。
タイトルとディスクリプションがほぼ同じ文言だと、情報量が少ないと見なされることがあります。また、検索結果で並んだときに「冗長な印象」を与え、他の結果よりも魅力的に見えないリスクもあります。
タイトルが「SEOの基本とは?初心者向け解説」だった場合、ディスクリプションでは「SEOの仕組みや必要性を、初心者にもわかるようにステップ形式で解説」といった具合に、補完的な情報を加えるのが効果的です。

手作業での調整には限界があるため、専用ツールを活用することで効率的かつ精度の高いメタディスクリプション作成が可能になります。ここでは、代表的なツールの活用方法と特徴を紹介します。
Google検索結果ではピクセル幅で表示領域が決まるため、文字数カウントだけでは不十分です。そこで役立つのが、検索結果のスニペット表示を模したシミュレーションツールです。
以下は代表的な無料ツールです。
これらのツールを使えば、「思ったより省略されてしまった」「スマホでは伝わり切らない」といった問題を事前に回避できます。特に複数デバイスでの確認は重要です。
最近では、AIを活用して検索意図やトーンに応じたメタディスクリプションを自動生成できるツールも登場しています。例えば、以下のような活用が考えられます。
AIはあくまで補助ツールであり、最終的な品質管理は人の編集力に委ねられます。
また、キーワードの不自然な羅列や、事実と異なる内容が含まれることもあるため、生成された文章は必ず精査しましょう。
| ツール名 | 特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| metadescription.io | 表示シミュレーションが可能。PCとスマホ両対応。 | 無料 |
| Ahrefs | キーワード分析・CTR推定・競合分析が可能 | 有料(月額制) |
| ChatGPT(Pro) | プロンプト次第で高品質な案を複数生成可能 | 無料(一部有料プランあり) |
| Yoast SEO(WPプラグイン) | メタ記述のプレビュー・最適化評価を提供 | 無料(有料版あり) |
使うツールの選定は「作成・表示チェック・分析」のフェーズごとに分けて考えると無駄がありません。必要に応じて併用することをおすすめします。

効果的なメタディスクリプションも、適切に設定されなければ意味がありません。
ここでは、主要なCMSごとに設定方法をわかりやすく解説します。
WordPressでは、「All in One SEO」や「Yoast SEO」といったプラグインを使用することで、簡単にメタディスクリプションを設定できます。以下は基本的な流れです。
プラグインを使用すれば、Googleに正しくmeta情報が送信されているかも確認しやすくなります。また、Yoastでは「ディスクリプションの質」の評価も表示され、改善ポイントが視覚的に把握できます。
静的なHTMLサイトや一部のCMSでは、以下のようにheadタグ内にmetaタグを直接記述する必要があります。
<meta name="description" content="ここにメタディスクリプションを記述">この際の注意点としては、
Googleが正しく認識できるよう、文法ミスやHTML構造の不備にも注意が必要です。
以下のような主要CMSでも、ページ単位でメタディスクリプションの設定が可能です。
これらのCMSはノーコードでも直感的に設定できる設計になっており、非エンジニアのWeb担当者でも対応しやすいのが特徴です。ただし、サイト全体で一貫性を保つためには、メタディスクリプションのルールやテンプレートを社内で共有することも効果的です。

メタディスクリプションは一度書いて終わりではありません。CTRを向上させるためには、定期的な分析と改善が必要です。ここでは、効果検証の手法や優先順位のつけ方を紹介します。
Google Search Consoleでは、各ページの検索クエリ別CTRや表示回数、平均掲載順位を確認できます。「検索パフォーマンス」から対象ページを選び、CTRが極端に低いページは、メタディスクリプションの改善対象と見なしてよいでしょう。
特に「表示回数が多いのにCTRが低い」ページは改善余地が大きく、少しのリライトで大きな成果を得られるケースも多くあります。
複数のメタディスクリプション案を用意し、数週間ごとに入れ替えることで、どちらが高いCTRを記録するかを比較できます。ABテストでは、クリック率以外にも、直帰率や滞在時間といったユーザー行動も参考にしましょう。
CMSやABテストツール(Google Optimizeなど)を用いると管理が容易になります。自動切り替えが難しい場合は、期間を決めて手動で実施しても効果はあります。
すべてのページを一度に改善するのは現実的ではありません。優先的に手を入れるべきは、以下のようなページです。
まずはこうしたページのメタディスクリプションを見直し、「ユーザーが求めている情報を的確に伝えられているか」「クリック後の満足度が高くなる構成になっているか」をチェックすることが重要です。
メタディスクリプションはSEOにおける「見られる入り口」として、CTRに大きく影響します。最適な文字数はPCとスマホで異なるため、表示される範囲内で価値を伝えることがポイントです。ユーザーの検索意図を捉え、自然なキーワードの挿入と具体的なベネフィット提示を意識すれば、成果につながるメタディスクリプションが実現できます。定期的な検証と改善を繰り返しながら、ユーザーにも検索エンジンにも伝わる説明文を構築していきましょう。
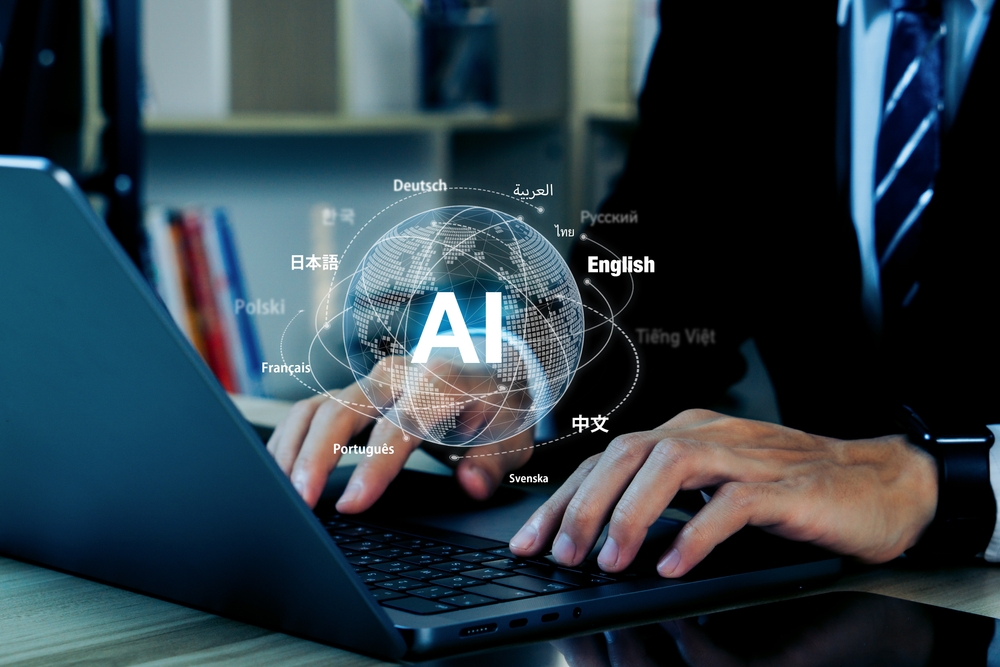
自分でSEO対策をしたいけど「方法がわからない」「うまく行くか不安」「リソースが足りない」という際はProteaにご相談ください。
サイトの状況を確認し、各社の課題にあった提案をさせていただきます。
お問合せはこちら
また、AI記事サービスの「AIフォースSEO」も提供しております。
AIフォースSEOは1記事5,000円から作成可能な記事生成サービスです。
キーワード選定がプラスされたプランもご用意しております。
SEO対策を実施したいけど、自社にノウハウがない、リソースが足りないなどでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
AIフォースSEOのお問合せはこちら
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。