オウンドメディアを立ち上げたものの「本当に意味があるのか?」と不安を感じていませんか。コストや運営の手間はかかるのに、想定ほどの成果が見えないと、挫折しそうになることもありますよね。
本記事では、オウンドメディアが意味ないと言われがちな理由と、成果を上げるための具体的なポイントを解説します。
運用のコツや成功事例、費用対効果の高さを実現するポイントなどを解説していきますので、オウンドメディアの立ち上げを検討している方や、現在運用中の方は是非、参考にしてください。
目次

オウンドメディアは企業や個人が自ら発信できる強力な情報発信ツールです。しかし、実際には「運営コストばかりかかって効果が感じられない」という声が後を絶ちません。なぜ「意味がない」とまで言われてしまうのか、その背景を具体的に見ていきましょう。
オウンドメディアの運用には、サイト構築費やコンテンツ制作費など、初期投資だけでも多くのコストがかかります。さらに継続的な運営には人件費やツールの導入費が必要です。この負担と得られる成果のバランスがとれないと「意味がない」という印象を抱きやすくなります。また、短期的な成果を求めすぎるあまり、十分な運用期間を確保できずに途中で断念してしまうケースも少なくありません。
ただし、オウンドメディアの効果はROI(投資対効果)を中長期で測ることが基本です。制作・運営コストに対してどの程度のリードや売上につながっているかを定期的に検証し、費用面で見合っているかを判断する必要があります。短期間で結果が出なくても、継続していくことでコンテンツが蓄積され、検索エンジンからの評価が高まるメリットも大きいのです。
適切な運用担当者の人件費、ライティングやデザインを外注するコストなど、オウンドメディアには想像以上の経費がかかります。
たとえば以下の項目は見落とされがちです。
こうした費用を正確に見積もらないまま始めてしまうと、いつの間にか予算をオーバーし、十分な成果を得る前に「意味がない」と判断してしまうことがあります。見積もり段階で運用期間まで含めた計画を立て、収益モデルや目標設定とリンクさせることが大切です。
オウンドメディアは基本的に中長期視点で取り組むものです。しかし、すぐに売上や問い合わせ数を増やしたい経営判断が優先されると、育成期間が必要なオウンドメディアでは結果が出にくく「費用に見合わない」と捉えられてしまいます。短期施策(広告など)と併せて、オウンドメディアの長期効果を考慮したプランを策定することが重要です。運営開始直後から華々しい成果を求めるのではなく、1年〜2年先を見据えた評価基準を設けることで「意味がない」との誤解を防げます。
オウンドメディアはただ闇雲に記事を増やせばよいわけではありません。ユーザーの悩みを解決する内容や、専門性が求められる分野をカバーしない限り、見込み顧客との接点づくりは難しくなります。また、運営側が思い描いているユーザー像と実際の顧客層がズレているケースもあり、その結果「読まれない」「問い合わせが来ない」という事態に陥るのです。
オウンドメディアで成果を出すためには、最初に「誰に向けて」「どんな価値を提供したいのか」を明確にする必要があります。ペルソナ設定が曖昧だと、テーマ選びや内容の深さがバラバラになり、読者に響きにくい記事が量産されてしまいます。ターゲットを具体的に想定し、日常の課題や欲求を掘り下げることで、読者が求める情報へ近づけられます。さらにペルソナの情報を定期的にアップデートし、市場や顧客の変化に対応できるよう心がけると、方向性のブレを防ぎやすくなります。
特にBtoB分野や高度な専門知識が求められる分野では、信頼できる情報であるかどうかが非常に重要です。専門性の低い記事や裏付けのないデータを用いてしまうと、ユーザーが離脱する原因になります。また、誤った情報を発信するとブランドイメージにも悪影響を及ぼします。そのため、記事に使用するデータや事例は信頼できるソースを引用し、根拠を明示しましょう。
近年では検索エンジンがコンテンツの「専門性・権威性・信頼性」を評価する傾向が強まっており、E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness)と呼ばれる基準が注目されています。正確な情報と独自の見解を組み合わせ、読者にとって価値あるコンテンツを提供し続けることがオウンドメディアの信頼性向上につながります。

「意味がない」状態に陥ってしまう背景を理解したら、今度は具体的な成功への道筋を考えましょう。ここでは、オウンドメディアで成果を出すうえで重要となるポイントや、日々の運営に役立つ実践ステップを紹介します。
まずはゴールを明らかにしないまま進めることが最大のリスクです。何を目的にオウンドメディアを立ち上げ、どのような成果を期待するのかを共有することで、運営の方向性がぶれなくなります。そのうえでKPIを設定することで、進捗を測りやすくし、適切な施策を講じられるようになります。
オウンドメディアの目標は事業のビジョンと結びついている必要があります。以下はKPI設計の一例です。
ここで重要なのは、「記事数を増やす」など単なる作業指標に終わらせず、売上やリード数といった事業指標を最終ゴールに据えることです。KPIを掲げたら定期的に数値を見直し、方向性がズレていないかを検証する体制を整えましょう。
KPIを定量的に追うためには、Googleアナリティクスやサーチコンソールなどのアクセス解析ツールを活用します。データを蓄積することで、どのコンテンツがユーザーの興味を引いているのか、問い合わせや購入につながっているかなどが可視化されます。継続的にデータを分析することで、成果が出ない場合の原因を特定しやすくなります。
たとえばアクセス数が伸びていても問い合わせが増えないなら、フォームの導線に問題があるかもしれません。逆にアクセス数は少なくてもCV率が高い記事があれば、それを増やす施策に注力すると効果的です。こうしたモニタリングを通じてKPIと実際の状況をすり合わせる作業が、オウンドメディアの改善を進めるうえで欠かせません。
どれだけKPIを設定しても、中身となるコンテンツが低品質であれば成果は見込めません。読者の悩みやニーズを深く捉えた文章を作り続けることが、オウンドメディア成功の大きなカギです。さらに、完成した記事を公開した後も、フィードバックを得ながら改善するサイクルを回す必要があります。
質の高いコンテンツを作るには、ユーザーが抱えている悩みを正確に理解することが不可欠です。具体的には次のような方法があります。
こうしたリサーチの結果をもとに、記事構成やキーワード選定を行うと、読者に刺さるコンテンツが作りやすくなります。単純に「ニーズを調べる」だけで終わらせず、顧客がどのような解決策を求めているのかを深く分析することで、説得力のあるコンテンツが作成可能です。
公開した記事が狙いどおりのアクセスや問い合わせを獲得しているかを定期的にチェックし、必要に応じてタイトルや内容を修正します。いわゆるPDCAサイクルを回すことが重要です。特にSEOの観点では、検索キーワードの動向や競合サイトの変化を追いながら更新し続けることで、検索結果での上位表示を狙えます。改善の手間を惜しまない姿勢が、長期的な成果につながります。
たとえば、検索順位が落ちている記事は情報が古くなっていないかを確認し、新しい事例や統計データを追加するなど、タイムリーな更新を行うとアクセス数が回復する可能性があります。常にユーザーの最新ニーズに対応していく意識が肝心です。
オウンドメディア単体での集客には限界があるため、SNSや広告などほかのチャネルと連携することが効果的です。さまざまな入り口を用意することで、見込み顧客との接触機会を増やせます。反対に、チャネルごとの役割やコンセプトが曖昧だと分散してしまうため、しっかり連携を考えた運用を心がけましょう。
検索エンジンからの流入を狙うSEOは、中長期的に安定したアクセスをもたらします。一方、SNSは拡散力とリアルタイム性に優れており、オウンドメディアに誘導するフックとして有効です。
SEOとSNSをうまく組み合わせると、以下のようなメリットが期待できます。
単にSNSでシェアするだけでなく、ユーザーのコメントやリアクションを分析し、次回の記事へ反映するといったフィードバックループを構築することで、よりターゲットに刺さるコンテンツが生まれやすくなります。
SNSだけでなく、広告やメールマガジンなども組み合わせるとより多くのユーザーに情報を届けられます。特に広告はターゲット設定がしやすいため、ニーズの高いユーザーを直接呼び込むことが可能です。また、メルマガは顧客との関係を維持しながらオウンドメディアの記事更新を告知でき、リピーターの育成に貢献します。運営コストとの兼ね合いを見ながら、適切な手段を選択しましょう。
さらに、メールマガジンの読者データをもとにクリック率やCV率を分析し、興味を持ちやすいテーマを優先的に記事化するといった施策も有効です。ポイントは、得られたデータを次の運用へ反映させる仕組みを作ることにあります。
オウンドメディアを継続して成長させるには、適切な運用体制の構築が不可欠です。限られたリソースのなかで最大限の成果を得るためには、社内外で専門性を活かしながら、無理なくチームで動ける体制作りが重要となります。
すべてを社内で対応しようとすると、特定のメンバーに負荷が集中しやすくなります。また、専門知識が必要な領域(SEOや高度なデザインなど)でクオリティを下げてしまうリスクもあります。そこで、要所によって外部の専門家や制作会社と協力することで、費用対効果を高められます。社内スタッフはコアコンテンツの企画やブランド戦略に集中しつつ、技術的サポートを外部に委託するなど、役割分担を明確にすることが大切です。
専門家とのやりとりでは、依頼内容を具体的に示し、成果物のチェックやフィードバックを迅速に行うことで質の高いアウトプットを保ちやすくなります。双方が「どのようなゴールを目指しているのか」を共通認識として持つことが、スムーズな連携の鍵となるでしょう。
運用が軌道に乗ると、コンテンツ量が増え、チェック体制や更新スケジュールの管理が複雑になります。そこで、記事制作や編集の流れをドキュメント化・テンプレート化しておくと、チーム全体の生産性がアップします。例えば記事の作成から公開までのフローを定義し、担当者ごとのタスクを可視化することで、進捗状況が把握しやすくなります。結果的に、無駄なやり取りや重複作業を減らすことができます。
また、編集スケジュールを管理するために「エディトリアルカレンダー」を導入すると、誰がいつどのテーマの記事を担当し、いつ公開するのかを一目で把握できます。これにより、作業の重複や締め切りの混乱を防ぎ、安定的にコンテンツを供給できるようになります。
オウンドメディアは、適切な戦略と継続的な運用によって確かな成果を生む可能性があります。意味がないと感じる多くのケースは、コスト面やコンテンツ面の準備不足や短期志向が原因です。運用目標を明確化し、質の高いコンテンツを持続的に発信しながら多角的な集客施策と組み合わせれば、長期的に大きなリターンを得られるでしょう。
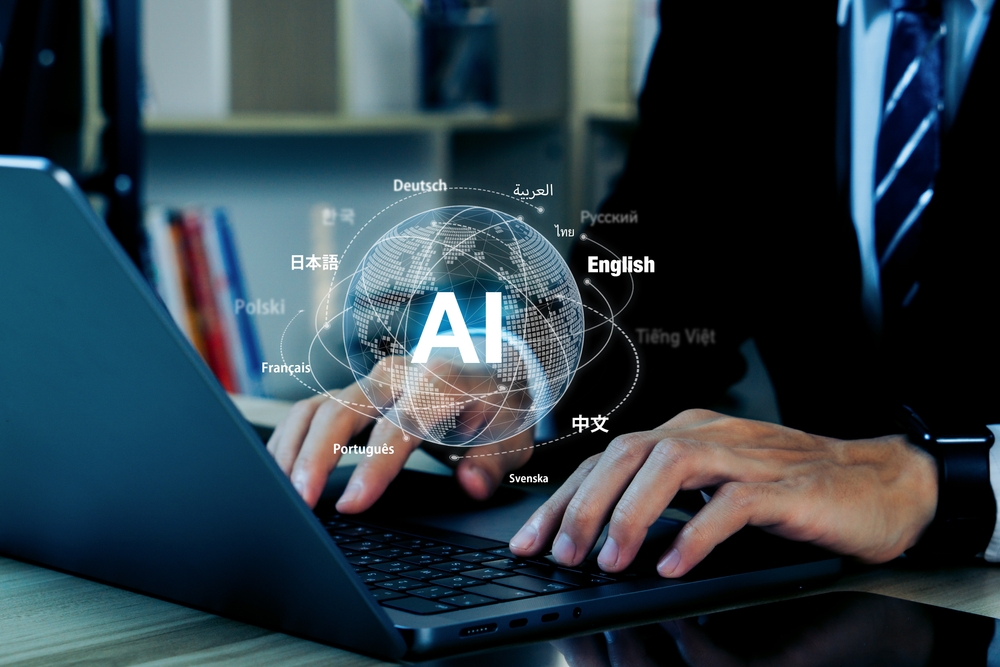
オウンドメディアを運用をしたいけど「方法がわからない」「リソースが足りない」という際はProteaにご相談ください。
ご希望や目的などをに併せ、各社にあった提案をさせていただきます。
お問合せはこちら
また、AI記事サービスの「AIフォースSEO」も提供しております。
AIフォースSEOは1記事5,000円から作成可能な記事生成サービスです。
キーワード選定がプラスされたプランもご用意しております。
SEO対策を実施したいけど、自社にノウハウがない、リソースが足りないなどでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
AIフォースSEOのお問合せはこちら
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。