「SEO対策って結局なにをすればいいの?」
そんな疑問を抱えたまま、なんとなく記事を書いては検索順位が上がらず悩んでいませんか?SEO対策は、検索エンジンに正しく評価されるための「基本の型」を押さえることが最も重要です。
本記事では、初心者でも理解できる「SEO対策の基本」をわかりやすく解説します。Googleの評価基準や検索意図の捉え方、コンテンツの作り方など、SEOに必要な基礎知識を体系的に習得できます。さらに、実際に取り組むべき施策についてもステップごとに紹介するので、「何から始めればいいかわからない」といった方にも安心です。
WebマーケティングやSEOコンサルの現場で培ったノウハウをもとに、信頼性の高い情報をお届けします。ぜひ、SEOの土台を固めたい方とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次

「SEO対策を始めたいけど、まず何から理解すればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。SEOを正しく進めるには、まずその定義と施策の全体像を把握することが重要です。ここでは、SEOの目的や基本構造を丁寧に解説します。
SEO(Search Engine Optimization)とは「検索エンジン最適化」の略で、Googleなどの検索エンジン上で自社のページを上位表示させるための施策全般を指します。目的は検索結果からの流入を増やし、集客・売上・認知拡大などのビジネス成果につなげることです。例えば広告と異なり、クリックされても課金されないため、長期的かつコストパフォーマンスに優れた集客手段として注目されています。現在では、多くの業界でSEOが競争力の源泉となっており、対策をしていないだけで機会損失に繋がることも少なくありません。
SEO対策は大きく「内部対策」と「外部対策」に分かれます。
内部対策は検索エンジンのクローラーが情報を正しく読み取り、ページを適切にインデックスするために不可欠です。例えば「適切な見出し構造」「タイトルタグの最適化」「サイトの表示速度」などが該当します。一方、外部対策は他サイトからの評価(被リンクなど)を通じて、ドメイン全体の信頼性を高めることが狙いです。双方をバランスよく実施することで、SEOの効果は大きくなります。

SEOを始める際は、いきなりコンテンツを作るのではなく、戦略設計からスタートすることが成功の鍵です。目的設定、ユーザー分析、キーワード選定、競合調査という「土台」をしっかり築くことで、施策の精度が格段に上がります。
まずは「なぜSEOを行うのか」というゴールを明確にしましょう。例えば「検索流入を月1,000件に増やす」「問い合わせを月30件にする」など、数値で測れる目標が理想です。また、誰に向けて情報を発信するのか、つまり「ターゲットユーザー」の設計も重要です。
ターゲットの年齢層、職業、悩み、検索行動などを具体化することで、コンテンツの方向性がブレず、検索意図にもマッチしやすくなります。例えばBtoB向けのSEO記事と一般消費者向けの記事では、使う語彙や事例の出し方も大きく異なります。
SEOにおいてキーワード選定は「設計図」とも言える重要な作業です。以下の手順で進めましょう。
無料ツールとしては「Googleキーワードプランナー」「ラッコキーワード」「Ubersuggest」が定番です。特にラッコキーワードは検索サジェストを一括取得できるため、「実際にユーザーがどんな言葉で調べているのか」を知るのに役立ちます。ただし、ボリュームだけでなく、競合の強さや、自サイトの強みとのマッチ度も考慮しながら選定する必要があります。
競合分析は「すでに検索上位にいるサイト」が何をしているのかを学ぶ貴重な機会です。調査時は以下の点に注目しましょう:
これらを分析することで、単に真似をするのではなく「どこで差別化できるか」「自社ならではの価値をどう打ち出せるか」という視点で自サイトを強化できます。競合に勝つには、“上位ページよりも検索意図を深く満たす”ことが最短ルートです。

SEOで上位を狙うには、Googleが何を基準にページを評価しているのかを理解する必要があります。評価基準は数百にのぼりますが、特に重要なのが「E-E-A-T」「検索意図の一致」「ユーザー行動データ」の3つです。
E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取った評価指標です。Googleはこの要素を使い、Web上の情報が信頼に足るものかどうかを判断しています。
例えば、医療・金融などのYMYL(Your Money or Your Life)領域では、このE-E-A-Tの比重が非常に大きく、医師監修や資格明記などが評価に直結します。情報の裏付け、実名著者の記載、実体験の記述なども重要な要素です。
キーワード選定だけでなく、そのキーワードに対する「検索意図」を正確に捉えることが、上位表示の前提です。
例えば、「SEO ツール 無料」と検索する人は、ツールの概要ではなく「比較一覧」や「おすすめランキング」を求めている可能性が高いです。逆に「SEO 対策 方法 初心者」であれば、体系的な解説を期待しているでしょう。
このように、キーワードの文字面だけでなく、「この言葉を検索した人は、何を解決したくて検索したのか?」を読み解き、それに応える構成・内容にすることがSEO成功のカギです。検索意図は競合上位10記事を分析すれば傾向が見えてきます。
Googleはユーザーがページを訪れた後の行動も重要視しています。特に以下の指標が評価に影響を与えます:
これらが悪化している場合、ユーザーにとってページが「期待外れ」だったと見なされ、検索順位が下がることもあります。改善のためには、冒頭に明確な結論を書く、見出しごとに価値ある情報を入れる、画像や図解を用いるなど、ユーザーがストレスなく情報を取得できる設計が必要です。

内部対策とは、自社サイトの構造・HTMLタグ・内部リンク・モバイル対応・表示速度などを最適化し、検索エンジンにとって「正しく解析しやすく、ユーザーにも使いやすい」状態に整える施策です。Googleが好む構造を作ることは、SEOの土台となります。
タイトルタグとメタディスクリプションは、検索結果に表示される重要な要素であり、ユーザーのクリック率(CTR)に大きく影響します。Googleはタイトルとページ内容が一致しているかどうかも確認するため、最適化は必須です。
タイトルは全角30文字以内で「具体性+ベネフィット+信頼性」を意識して設計しましょう。例えば「SEO初心者向け!今日から始める基本対策ガイド【無料ツール付き】」のように、対象・利点・特典を含めるとクリックされやすくなります。
メタディスクリプションは90〜120文字を目安に、ページの内容とユーザーの悩みに対する解決策を簡潔に提示しましょう。検索キーワードが含まれると太字で強調されるため、自然に含めると効果的です。
Hタグ(H1〜H4など)は、コンテンツの構造を示す重要な要素です。H1は原則1ページに1つ、ページの主題を明確に示す役割を持ちます。H2〜H4は階層構造に従って使用し、適切に整理することでクローラーもユーザーも内容を理解しやすくなります。
また、見出しにキーワードを入れることも推奨されますが、不自然な詰め込みはNGです。あくまで「見出しを読むだけでも内容がわかる」構成が理想です。読者が求める情報をスキャンしやすくなり、滞在時間の向上にもつながります。
内部リンクは、サイト内のページ同士を適切に繋げることで「サイト全体の構造理解」を促す重要な要素です。関連コンテンツへのリンクや、カテゴリトップページへのリンクを意識して設置することで、ユーザーの回遊率も向上します。
Googleのクローラーが全ページを適切に巡回・インデックスできるように、「XMLサイトマップ」の作成とSearch Consoleへの送信は必須です。併せて「HTMLサイトマップ(ユーザー向け)」も用意することで、訪問者が目的のページにたどり着きやすくなり、直帰率の改善にも寄与します。
Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、スマートフォンでの表示が検索順位に直接影響します。表示速度が遅ければ、離脱率が上がりSEO評価にもマイナスとなります。
「PageSpeed Insights」や「Core Web Vitals」を活用し、画像の圧縮、コードの軽量化、遅延読み込み(Lazy Load)などの技術を取り入れて、モバイルでも快適に表示できるようにしましょう。

検索順位に直結するのは「質の高いコンテンツ」です。いくら構造が整っていても、内容がユーザーの期待に応えていなければ、上位表示は望めません。ここでは、良質なコンテンツを作るための基本を解説します。
検索エンジンが評価するコンテンツは、「ユーザーの検索意図」にしっかり応えているものです。たとえば「SEO チェックリスト」と検索するユーザーは、概念ではなく、すぐに使える項目リストを期待している可能性が高いです。
そのため、記事を作る前に「このキーワードで検索する人が何を知りたいのか?」を分析し、それを満たす構成と情報を盛り込むことが大切です。Googleは単なる情報の寄せ集めよりも、ユーザーの疑問を解消することに重きを置いています。
SEOにおけるキーワード配置は、「検索エンジンに内容を正しく伝えるため」の施策です。主に以下の箇所に自然な形で含めるのが効果的です:
ただし、無理に詰め込むと読みにくくなり、ユーザー満足度が下がってしまいます。共起語や関連ワードも活用することで、より自然で文脈に沿ったライティングが可能です。
一度公開した記事でも、内容が古くなれば順位は低下していきます。情報の鮮度はGoogleの評価基準の1つであり、特にトレンド性のあるテーマでは定期的な更新が求められます。
更新の際は、事実の修正だけでなく、検索意図の変化や競合の変化も考慮して見直しましょう。目安としては3〜6ヶ月に1度はリライトを検討するとよいでしょう。
同じ内容を複数のページで扱うと、Googleはどのページを評価すべきか判断できず、順位が分散します。これを防ぐためには、canonicalタグの設定や、記事の統合、不要なページの削除が有効です。
また、内容が薄い記事(文字数が少ないだけでなく、情報価値が乏しいもの)はサイト全体の評価を下げる原因になります。ユーザーが「読んでよかった」と思える独自性のある視点や情報を盛り込むことが大切です。

外部対策とは、サイトの外からの信頼性を高める施策のことです。特に被リンク(バックリンク)の質と量は、現在でもSEOに強い影響を与えています。
被リンクとは、他サイトから自サイトへのリンクを指します。Googleは「推薦」と捉えており、信頼性や評価の指標となります。ただし、やみくもに増やせばいいわけではなく、リンク元の質が重視されます。
被リンクを得るには:
これらは自然なリンク(ナチュラルリンク)を生み出すための基本的な取り組みです。
権威性の高いサイト(新聞社、行政機関、大学、業界団体など)からのリンクはSEOに非常に強い影響を与えます。信頼性のある発信を行うことで、自然とこうしたリンクを獲得しやすくなります。
実際には、プレスリリースの配信、セミナー登壇、業界団体との提携など、オンライン外の活動がきっかけになることも多いため、オフライン施策も視野に入れましょう。
リンクは「欲しい」とお願いするものではなく、「貼りたい」と思わせるものです。そのためには、価値ある情報・便利なツール・一次情報などを提供し、他者からの引用・紹介を促進しましょう。
「チェックリスト」「統計」「テンプレート」「業界トレンド」などはシェアされやすい形式です。またSNSやYouTubeを活用して露出を増やすことで、被リンクのチャンスも広がります。

SEOは施策を打って終わりではありません。成果を確認し、改善し続けることが求められます。適切な効果測定ツールを使い、指標に基づいて次の一手を考えましょう。
Search Consoleでは「表示回数」「クリック数」「平均順位」「インデックス状況」などを確認できます。Analyticsでは、「どのページに何人訪れて、何秒滞在したか」といったユーザー行動が分析できます。
これらの情報を定期的にチェックすることで、改善すべきページや、成果が出ているコンテンツの傾向が見えてきます。
検索順位は日々変動しますが、明確な落ち込みがあれば原因の特定が必要です。要因としては以下のようなものが考えられます:
Search Consoleのエラー表示や、上位ページの変化を観察することで手がかりが得られます。
SEO改善はリソースを効率的に使うことも重要です。以下のような観点で優先順位を決めましょう:
改善の効果が高い箇所から取り組むことで、限られた工数でも成果を最大化できます。
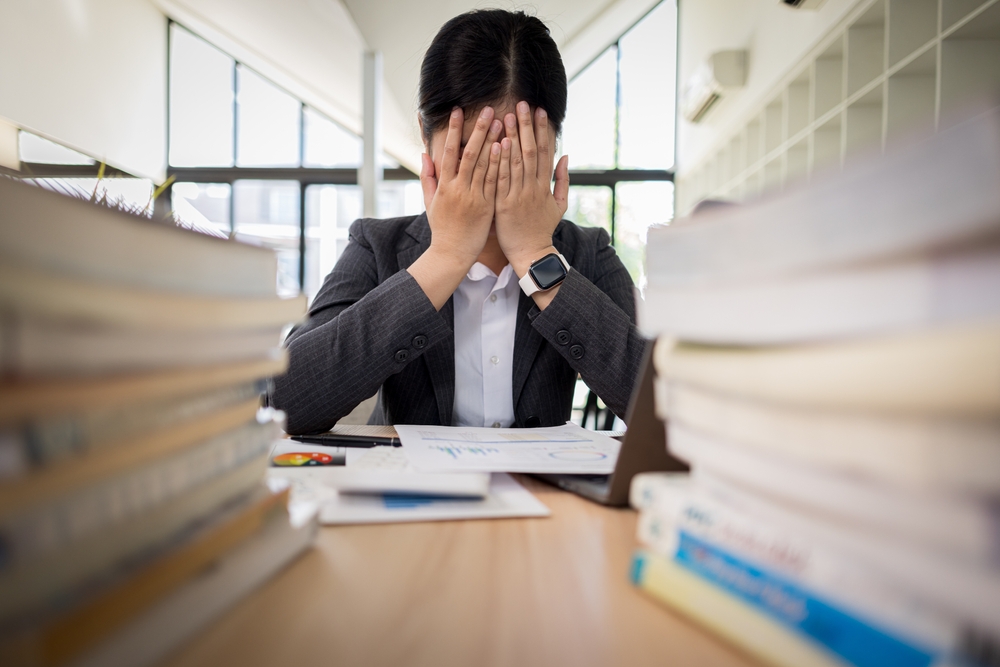
SEOを始めたばかりの方が陥りやすい失敗を知っておくことで、無駄な作業や評価の低下を防ぐことができます。
キーワードを意識しすぎて、文章が不自然になるケースが非常に多いです。Googleは「自然な文脈でキーワードが使われているか」を見ており、過剰な挿入はスパム判定のリスクにもなります。
「更新頻度を上げれば評価される」と誤解し、質より量を重視してしまうパターンです。内容が浅い記事を量産しても、ユーザー満足度が低ければ逆効果です。1記事1記事を丁寧に作る方が長期的に見て効果的です。
SEOばかりに気を取られ、読みづらいレイアウトやリンク導線の不備が放置されることがあります。特にスマホ表示では、ボタンが押しにくい、スクロールが多すぎるといったUXの欠点が致命的になります。検索順位だけでなく、ユーザー満足度もSEOの一部です。

SEOはツールを活用することで、効率的かつ精度高く実施できます。
ここからは、目的別におすすめのツールを紹介します。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Googleキーワードプランナー | 検索ボリュームや競合性を調査できるGoogle公式ツール |
| ラッコキーワード | サジェストキーワードを一括取得、検索意図の把握に最適 |
| Ubersuggest | 検索ボリューム推定や競合分析も可能なオールインワンツール |
Search ConsoleでCTRや掲載順位を確認しつつ、「GRC」や「Rank Tracker」などを使えばキーワードごとの順位変動も追跡可能です。Ahrefsでは、上位ページのコンテンツ構成も分析でき、リライトの参考になります。
競合サイトの被リンク元やキーワード流入を調査するには「Ahrefs」「SEMrush」「Moz」などのツールが有効です。競合の成功施策を見つけて自社にも応用できます。
SEO対策は「検索エンジン」と「ユーザー」の両方に評価されるための工夫です。基本となる内部対策・コンテンツ改善・外部評価の3本柱をバランスよく進めることが成果につながります。地道な改善の積み重ねが、やがて大きな成果を生みます。
まずは「検索意図に応えること」を起点に、優先順位をつけて取り組んでいきましょう。
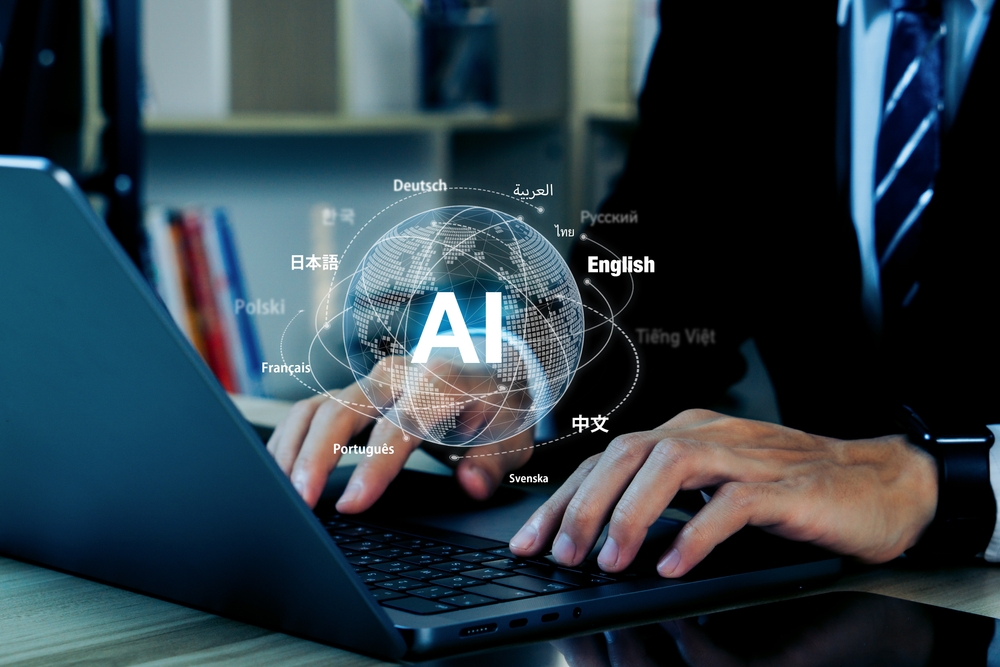
SEO対策をしたいけど「方法がわからない」「リソースが足りない」という際はProteaにご相談ください。
サイトの状況を確認し、各社の課題にあった提案をさせていただきます。
お問合せはこちら
また、AI記事サービスの「AIフォースSEO」も提供しております。
AIフォースSEOは1記事5,000円から作成可能な記事生成サービスです。
キーワード選定がプラスされたプランもご用意しております。
SEO対策を実施したいけど、自社にノウハウがない、リソースが足りないなどでお困りの際はぜひ一度ご相談ください。
AIフォースSEOのお問合せはこちら
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 プロテア
WEBマーケティングの領域で様々な手法を使い、お客さまの課題を解決する会社です。